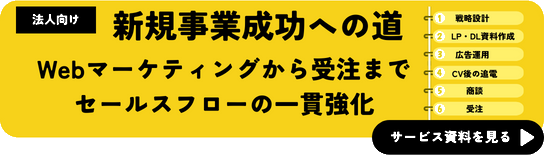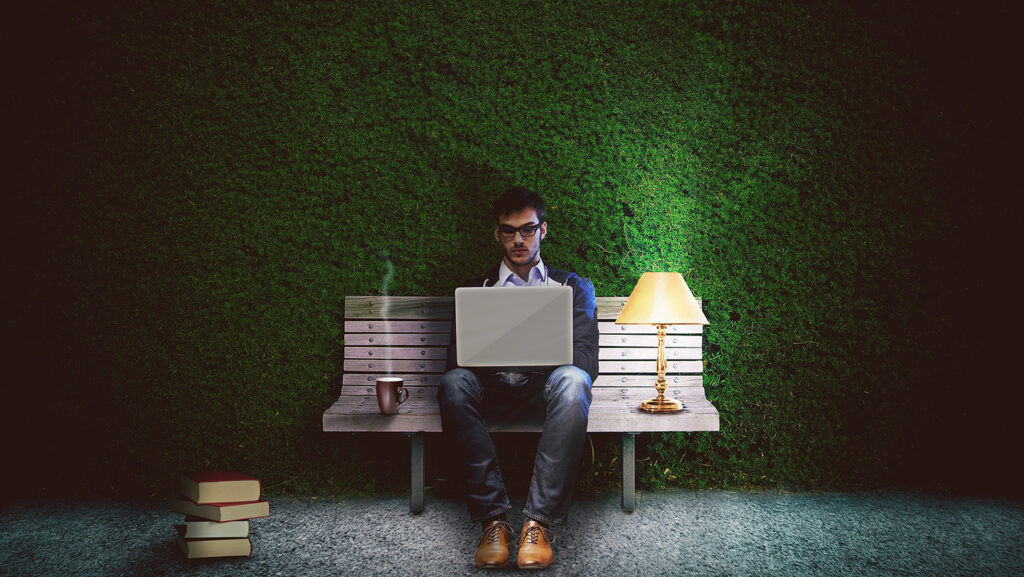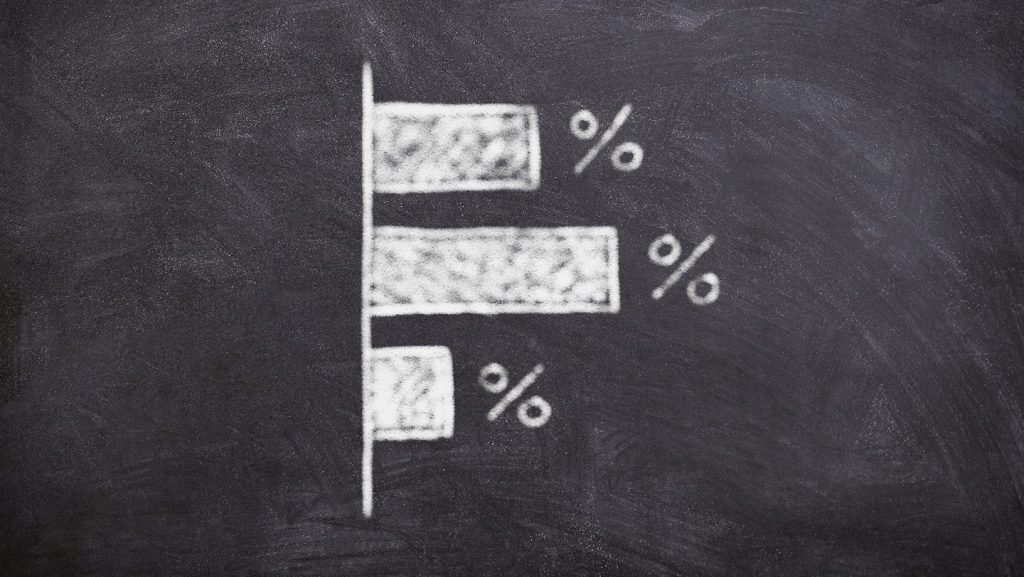人手不足なのになぜ雇わないのか?優秀な人材を求める企業と求職者のギャップを解説

「人手は足りないけれど誰でもいいわけではない」、「経営が苦しく新たに人を雇う余裕がない」など、人手不足でありながら、新規採用を躊躇してしまう理由はさまざまですよね。
本記事では、人手が足りていないのに雇わない理由や、人手不足が深刻だが、採用に踏み切れない経営者の悩みを紐解き、原因を解説していきますので、自社にどのようなケースが当てはまるかを考え、人手不足倒産を防ぐための予防や対策にぜひ役立ててください。
人手不足のお悩みの中小企業の方へ
優秀な社員が辞めない、人手不足に悩まない会社づくりの方法がわかる資料
人手不足に悩む中小企業が「在宅チーム」を活用することで、
優秀な社員を確保し、利益率の高い組織をつくる方法のヒントが得られます。
本記事では紹介しきれない人手不足の解決につながるヒントをご紹介していますので
以下のボタンからぜひダウンロードしてみてください。
人手不足の現状と採用できない主な理由

人手不足の現状
日本の高齢化と少子化により、労働力人口が減少しており、2020年の約7600万人から2025年には約7000万人に減少する見込みです。この人手不足はさまざまな分野に影響を及ぼし、サービス品質の低下、生産性の低下、コストの増加、事業縮小や廃止などのリスクが高まっています。
政府や企業は対策として、以下の施策を実施していますが、解決にはまだ時間がかかる見通しです。
- 外国人労働者の受け入れ拡大
- 女性や高齢者の就労促進
- テレワークやフレックスタイムの導入
- AIやロボットの活用
- 労働環境改善
- 賃金引き上げ など
人手不足なのに採用できない主な理由
主な理由として以下の3つが挙げられます。
- 人件費を賄う売上をたてられない
- 経験者求人が増加傾向にある
- 人材の定着率が低下している
①人件費を賄う売上をたてられない
会社の経費の中で、一番コストが重いものは人件費です。人を一人雇うためにかかるコストは毎月の給与だけではなく、交通費や各種保険料など相当な額になりますよね。それを賄えるだけの売上が上がる見込みがなければ、新たな働き手を雇うことはできません。
2022年の人手不足に対する企業の動向調査によると、人手不足の影響で売上が減少した企業の割合は28.9%で、最も多い回答でした。また、人手不足の影響で人件費が増加した企業の割合は38.6%で、2番目に多い回答となっています。
②経験者求人が増加傾向にある
どのような業種でも、即戦力を採用できれば教育のコストを減らせますからありがたいですよね。「未経験者から育てよう」という考えを持つ経営者や人事担当者は多くいますし、実際に「未経験者歓迎」と採用要件に書いている企業もありますが、それも限界があります。
未経験者を採用し、数か月かけて教育したにも関わらず、半年も経たずに退職してしまうケースも後を絶たず、そのような採用の失敗が続けば、会社全体が疲弊し売上の低迷や既存社員のモチベーションの低下にもつながりかねません。 そのような理由から一定以上の職務経験を持つ人を優遇する「経験者求人」をかける企業が増加傾向にあります。
2022年の求人・求職動向調査によると、求人倍率は1.64倍で、過去最高の水準でした。
現在は、求人倍率が高い「売り手市場」であり、かつ経験者求人が増加傾向のため、求人を出しても応募者が来ないという状態が進んでいると推測されます。
※求人倍率:【労働者有利】売り手市場(1以上) ↔︎ 【企業有利】買い手市場(1以下)
③人材の定着率が低下している
現代の日本では、終身雇用の概念は失われ、多様な働き方を求めて積極的に転職する人が増えました。ただ、企業としては定着率が低下すると、採用コストや教育コストが増加し、経営に悪影響を及ぼします。また、人材の流出は、業務の品質や顧客満足度の低下にもつながります。
例えば、人材紹介会社を活用した場合、1人採用するために100万円前後はかかります。
高いコストをかけて採用した人材に定着してもらえなかったリスクを考えると、安易に採用活動を行えない現状があります。
。
2022年の定着率・離職率調査によると、正社員の定着率は85.0%、離職率は15.0%でした。前年の定着率である86.1%と比較すると1.1%低下しています。
定着率の低下に繋がる要因は、以下の2点が挙げられます。
- ポテンシャル採用
- 働き方の多様化
※ポテンシャル採用・・・・
経験よりも潜在能力を重視し、経験の有無に関係なく採用する方法です。「キャリア採用(経験者)」より大きな母集団を形成できますが、育成を前提とした採用であるため、戦力になる保障がなく、採用のリスクが高くなります。また、一般的にポテンシャル採用の人材は離職率が高い傾向にあります。
※働き方の多様化・・・・
現代では、終身雇用が過去のものとなり、ワークライフバランスが重要視されています。企業が多様な働き方に対応できない場合、離職率が高まります。
育児や介護などの支援制度がない、または名ばかりで利用しづらい状態であれば、労働力を失うだけでなく、社員の会社へ不信感を募らせます。
この記事をご覧の方にオススメの資料のご案内
営業チームを内製化する方法がわかる資料
人材の確保や活用について課題をお持ちの中小企業が、 効果的に人材を活用するためのポイントと営業を内製化させていくためのヒントが得られます。
人手不足が深刻な職種ランキング【1位から5位】
- 土木職:有効求人倍率は5.60倍。
建設業界全体で人手不足が顕著。 - 介護関係職種:有効求人倍率は3.38倍。
2025年には約55万人の人材不足を予想。 - サービス職:有効求人倍率は2.82倍。
飲食などのサービス業界は非正規雇用率や短期離職率の高い。 - 運送業職種:有効求人倍率は1.32倍。
ECサイトの拡大により運送需要が増加する一方、ドライバーの減少や社員の高齢化が進む。 - 情報サービスの職業:有効求人倍率は1.32倍。
DXやマーケティングにかかせない情報処理や情報サービス業は近年成長を続けているが、優秀な人材の育成に時間がかかる。
※2023年4月時点。指標:有効求人倍率
※有効求人倍率とは、過去3ヵ月間の求職者数と求人数の割合で計算されたもので、労働市場の需要と供給のバランスを示すものといえます。例えば、2021年10月の有効求人倍率は1.15倍でしたが、これは2021年8月から10月までの求職者数と求人数の割合を表しています。
この記事をご覧の方にオススメの資料のご案内
営業チームを内製化する方法がわかる資料
人材の確保や活用について課題をお持ちの中小企業が、 効果的に人材を活用するためのポイントと営業を内製化させていくためのヒントが得られます。
人手不足企業の4つの特徴と解決策とは?

生産年齢人口が減少する中、有効求人倍率の増加や、採用を進められない理由があるなど、人材不足に陥る要因はさまざまです。
ただ、業界に限らず人手不足に陥りがちな企業には4つの特徴があります。
人手不足企業の4つの特徴
- 採用条件が不適切
- 労働環境が整備できていない
- 属人的な業務が多い
- 生産性が低い
4つの特徴の解決策
①採用条件が不適切における解決策:
採用ターゲットの明確化
採用に関する問題が生じた際、採用条件が適切でない可能性が高いです。
部署ごとに必要な人材を明確にし、社内でヒアリングを行い、採用ターゲットを明確化しましょう。
これにより、求人広告の無駄やミスマッチが減少し、コスト削減にもつながります。
②労働環境が整備できていないにおける解決策:
労働環境の見直し
社員の流出や健康問題が増えた場合、労働環境を見直す必要があります。 長時間労働、休日出勤、有休取得の難しさ、ハラスメントなど、社員の悩みに気づいていないだけかもしれません。
これらの問題は、労働基準法違反につながりかねません。
まずは、社員が相談しやすい機会づくり(秘匿性のある人事部との接点作り)や定期的なアンケートの活用を通じて、現場の問題を把握しましょう。問題の把握ができたら、労働環境の改善について検討していきます。
現場で起きている問題を把握し、それに合わせた改善の手段を検討し実施していくことが重要となります。
③属人的な業務が多いにおける解決策:
業務の標準化
・業務のブラックボックス化
・急な退職に対応できない
・やめられる怖さから適切な指導ができない
など、業務の属人化は多くのデメリットを招きます。
この属人化の原因としては、人材が不足し、業務内容を共有できる従業員が他にいないことが考えられます。
特に専門的な業務は属人化しやすく、担当者以外が理解しづらいこともあります。これにより、上司の評価が難しくなり、他の社員とのコミュニケーションが不足し、職場環境が悪化する可能性が高まります。この問題に対処するためには、マニュアルの作成や業務フローの可視化を通じて、業務の標準化を進めることが不可欠です。
④生産性が低いにおける解決策:
生産性の向上
「生産性が低い」とは、「従業員一人当たりの利益が低い」つまり社員が無駄が多く効率が悪い働き方をしているということです。
日本の労働生産性は先進7ヵ国の中でワースト1位であり、長くその状態が続いています。OECDのデータによると、2019年(最新)の日本の年間労働時間は先進7ヵ国の中で最も長く、有給休暇の取得率は最も低かったです。
このデータから、日本では時間をかけることで仕事を進めようとする傾向が強いことが推測でき、この進め方をしていると人手が足りないことがより深刻な状況をもたらします。
ただ、日本企業は働いた時間分の給与を支払う形態になっているため、生産性が低ければそれだけ利益を圧迫され、さらに人を増やすという決断をしにくくなっていきます。 人手不足を感じる時こそ、人手を増やすのではなく生産性の向上に目を向けていきましょう。
この記事をご覧の方にオススメの資料のご案内
営業チームを内製化する方法がわかる資料
人材の確保や活用について課題をお持ちの中小企業が、 効果的に人材を活用するためのポイントと営業を内製化させていくためのヒントが得られます。
remodooo!のご紹介~在宅チームで最強組織を~
人口減が進み、市場が縮小傾向にある日本において
社員の生産性を向上させ、自社の営業・集客・採用の力を強化させることが、これからますます重要になっていきます。
それを実現する解決策こそが、「在宅チーム構築」です。