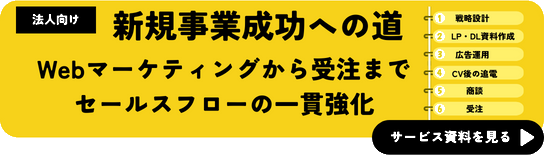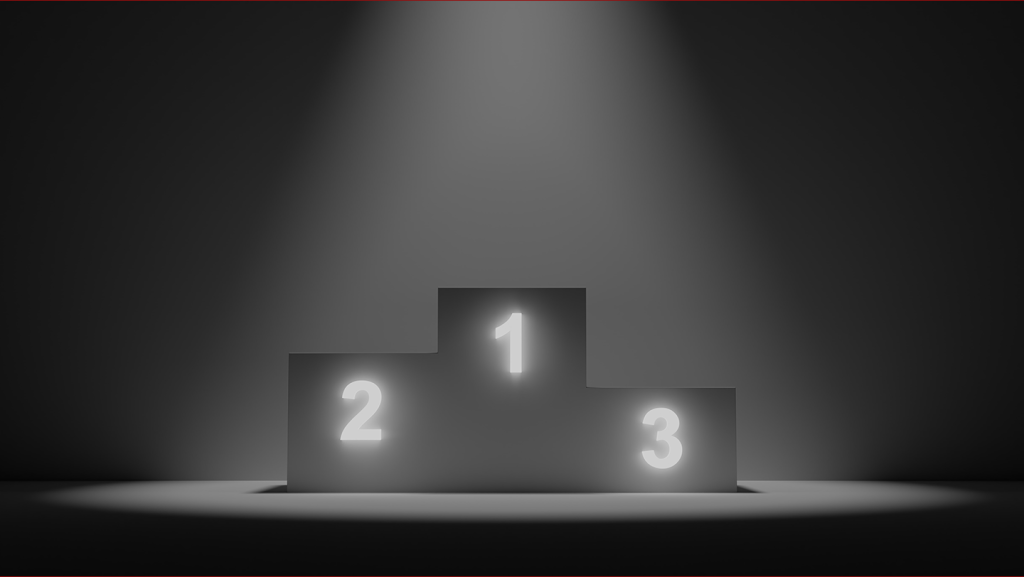仕事における役割分担の意味とは?メリットや課題を詳しく解説

「仕事における役割分担の意味がいまいち分からない」という方は多いのではないでしょうか。誰でも一度は役割分担という言葉を聞いたことがあると思いますが、その定義を説明するのは意外と難しいです。
そこで今回の記事では、仕事における役割分担の意味やメリット、課題などを詳しく解説していきます。役割分担は生産性やモチベーション向上などにつながるので、ぜひ参考にしてください。
この記事をご覧の方にオススメの資料のご案内
優秀な社員が辞めない会社づくりの方法がわかる資料
人手不足に悩む中小企業が「在宅チーム」を活用することで
優秀な社員を確保し、利益率の高い組織をつくる方法のヒントが得られます。
なぜ役割分担を行うのか

仕事における役割分担とは、業務で期待される役目の負担を分け合うことです。 一般には、分業した方が効率性が向上するときやメンバーの専門性が高いとき、メンバーの主体性を高めたいときなどに行われます。
ただ、基本的にチームで仕事を進める場合、「誰が、何を、どの範囲までやるべきなのか」が明確になっていないと、メンバーは迷い、リーダーはプロジェクトをスムーズに進めることが困難になっていきます。この役割分担は、組織の人数が増えるほど、できていないことが深刻な問題になっていきます。
また、役割分担によって自分の業務が明確であるほど、メンバーは責任感を高め、自分の仕事に対する理解と取り組みやすさを促進します。 その結果として、モチベーションが向上します。
モチベーションの向上が企業にもたらすメリット- 労働生産性の向上
- 離職率の低下
- 自発的なスキルアップや資格取得の促進
- 社内全体の士気向上
チームで仕事を進める上で、コミュニケーションを活性化させ、プロジェクトをスムーズに進め、成功させるためには、チームリーダーの行う役割分担(割り当てる仕事の明確化と適材適所の人材配置)は非常に重要といえます。
役割分担で得られる効果

上記で紹介した「モチベーションの向上」を含め、役割分担で得られる効果は、以下の4つがあります。
- モチベーション向上
- 生産性向上
- チーム体制の強化
- 企業規模の拡大
下記では、それぞれの効果を詳しく解説します。
生産性向上
メンバー自身が役割分担によって遂行するべき業務を把握できるため、スムーズにタスクをこなせるようになります。結果として、パフォーマンスが上がり、生産性向上につながります。
一方で、メンバーごとに対応する業務が決まっておらず、適当に割り当てている場合、業務のクオリティが低く、やり直しが増えてしまう可能性が高いです。結果的に、パフォーマンスが下がり、生産性も低下する恐れがあります。
モチベーション向上
メンバーの個性やスキルに適した役割分担を行うことで、メンバーが自身の能力を発揮できるようになり、モチベーション向上につながります。
メンバーのモチベーションが向上すると、定着率の向上も期待できます。
現在、日本では少子高齢化による人材不足が深刻化しています。そのため、人材の定着が課題となっている企業も多いです。そのような観点からも、役割分担を通してモチベーション向上につなげるのは非常に重要です。
チーム体制の強化
役割分担によりメンバーのモチベーションが高まり、主体性を持って働けるような環境を作ることで、責任感が生まれます。
業務に対して責任感が強まれば、無責任な遅延が発生することは無くなるでしょう。メンバーのスキルや意識の向上は、チーム体制の強化につながります。
チーム体制が強化されると、少し遅れが発生しているメンバーの業務をサポートできるようになります。メンバー同士が支え合うという組織風土も生まれ、働きやすい職場を実現できます。
企業規模の拡大
前述した通り、各メンバーの役割が明確になると生産性が向上します。生産性向上は、企業の成果につながるため、企業の売上アップが期待できます。結果として、企業規模の拡大につながります。
よく企業には、「10人の壁」「30人の壁」という言葉があります。10人の壁は売上、利益の大きさによって超えられるかどうか、30人の壁は組織作りの成果で超えられるかどうかが決まると言われています。
企業規模を拡大したい場合は、「組織作り=役割分担」という意識を持ち、会社運営を進めていくことが大切です。
多くの企業が陥りやすい、役割分担の課題と解決策

役割分担は売上拡大・組織拡大のために大きな効果を発揮しますが、多くの企業が陥りやすい課題も存在します。
企業が陥る役割分担の課題
- 業務が属人化する形での分担
- 分担する側とされる側の認識齟齬
①業務が属人化する形での分担
多くの企業は、「人に仕事を担わせる」ことで、役割を分担している場合が多いです。そのため、担当者がいないと業務が回らなくなってしまうリスクがあります。
解決策:属人化しない体制構築担当者が休職や退職した場合でも、業務を滞らせないようにするには、誰でも対応できるようにしておくことが必要です。
具体的には、業務フローの整理とマニュアル化が挙げられます。 業務フローを整理し、作業をマニュアル化することで、、誰でも対応できるようになること以外に、誰が対応しても同じ結果を出せることがメリットとして挙げられます。
②分担する側とされる側の認識齟齬
管理職と社員、リーダーとメンバーの間で役割分担の認識に齟齬があれば、上手く業務が回りません。
解決策:組織の目標を浸透させる組織の目標を達成するために役割分担を行うことを、社員一人ひとりに浸透させることが重要です。
役割分担の作業は、リーダーが1人で行うのではなく、可能な限りチーム全体で役割分担を行いましょう。 役割分担の作業に実際に携わることで、メンバーも役割を自分ごととして捉えられるようになります。
役割分担を進める4ステップ

役割分担をする際は、ステップを踏む必要があります。具体的には、以下の4ステップが必要です。
- 自分の業務を自分で棚卸しする
- 棚卸した業務を精査する
- スキル・工数・優先度に応じて人員を配置する
- 役割分担表を作成する
下記では、それぞれのステップを詳しく解説します。
業務を棚卸しする
まずは、業務を担当するメンバー自身で、業務を棚卸しします。業務の棚卸しを行うことによって、業務が「見える化」されます。
業務の棚卸しを行う際は、以下の方法がおすすめです。
①自身が対応している業務を書き出します。可能な限り細かい部分まで書くことが重要です。
②業務を「大分類」「中分類」「小分類」の3階層に分けて記入します。どんな業務が存在するのか一目で分かるようにするのが目的です。
③業務量の調査を行います。「どの業務にどれだけの時間を費やしているのか」を分単位で記入します。一回にかかる時間や業務が発生する頻度、年間業務量なども算出しましょう。
棚卸した業務を精査する
次に、棚卸した業務に対して無駄はないか、改善できる点はないか精査します。その結果、業務の「ムリ」「ムダ」「ムラ」が省かれ、生産性向上につながります。精査する具体的なポイントは、以下の通りです。
①その業務は本当に必要か
「業務の目的を説明できるかどうか」で判断します。
②他に必要な業務はないか
「必要だが、他の業務に時間を取られてできていない業務はないか」「将来のために今やるべき業務はないか」を考えます。
③どの業務に一番時間をかけているか
「それほど時間をかける必要があるか」「現状よりも少ない時間で対応できないか」を考えます。
④業務を細分化しすぎていないか
「他のメンバーと被っている業務はないか」「集約化・専門化できないか」を考えます。
⑤仕事に偏りはないか
「特定の人に偏っていないか」「繁忙期と閑散期が極端でないか」を考えます。
⑥メンバーの能力を有効活用できているか
「能力以上、以下の業務を任せていないか」を考えます。
⑦業務は標準化されているか
「自己流でやっていないか」「誰が対応しても同じ結果が出るか」「いつでも他のメンバーに引き継げるか」を考えます。
スキル・工数・優先度に応じて人員を配置する
業務を精査し終えたら、スキル・工数・優先度に応じて人員を配置します。適材適所の人材配置は、業務効率化や生産性、定着率の向上につながるため、非常に重要です。
反対に、適材適所の人材配置ができていないと、メンバーの不満が募り、生産性やモチベーションの低下、最悪の場合、離職の原因にもなりかねません。
各メンバーの得意・不得意、性格などのパーソナル情報を考慮した上で、配置しましょう。正しいパーソナル情報を得るためには、日頃から社員とコミュニケーションを取ることが大切です。
役割分担表を作成する
最後に、人材の配置が終わったら役割分担表を作成します。役割分担表を作成することで、役割が見える化され、メンバーの意識向上につながります。
また、他メンバーの役割も把握できるようになるため、コミュニケーションも円滑化されるでしょう。
管理職側は、メンバーの管理がしやすくなることがメリットです。分担表を作成する際は、後から編集しやすい構成にすることをおすすめします。
メンバーの異動や退職などで、役割が変更になる場合があるためです。役割分担表の効果を最大化するために、見やすさも考慮して作成します。
仕事を役割分担し組織力を高めよう!

今回は、仕事における役割分担の意味やメリット、課題などを詳しく解説しました。
役割分担を行うことで、各メンバーが対応するべき業務が明確になるため、モチベーションや生産性の向上につながります。
ただし、適材適所の人材配置ができていないと、モチベーションや生産性の低下、最悪の場合だと離職につながる恐れもあるため注意が必要です。リーダーとして人材配置を進める時は、各メンバーとのコミュニケーションを深めることで理解し、得意・不得意、性格などを考慮した上で配置を行いましょう。
どのような企業でも、チームで仕事を進める際の役割分担は極めて重要です。 役割分担を実施する時間が取れない、または適切に実施できるかどうかに不安がある場合は、専門的なアドバイザーやコンサルタントなどの第三者の助言を求めることで、より効率的に業務を整理することが可能になります。
役割分担を進めることで業務フローが明確になり、作業のマニュアル化が進むと、業務のアウトソーシングができるようになるため、社員がコア業務に集中することで生産性が向上します。
そして、アウトソーシング先を「在宅ワーカー」のチームとして構築することで、人件費を変動費化できるため、利益率の高い組織を作ることができるようになります。