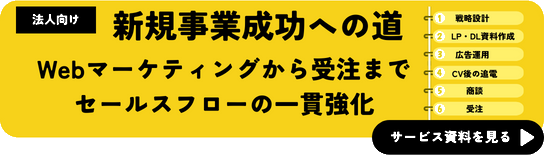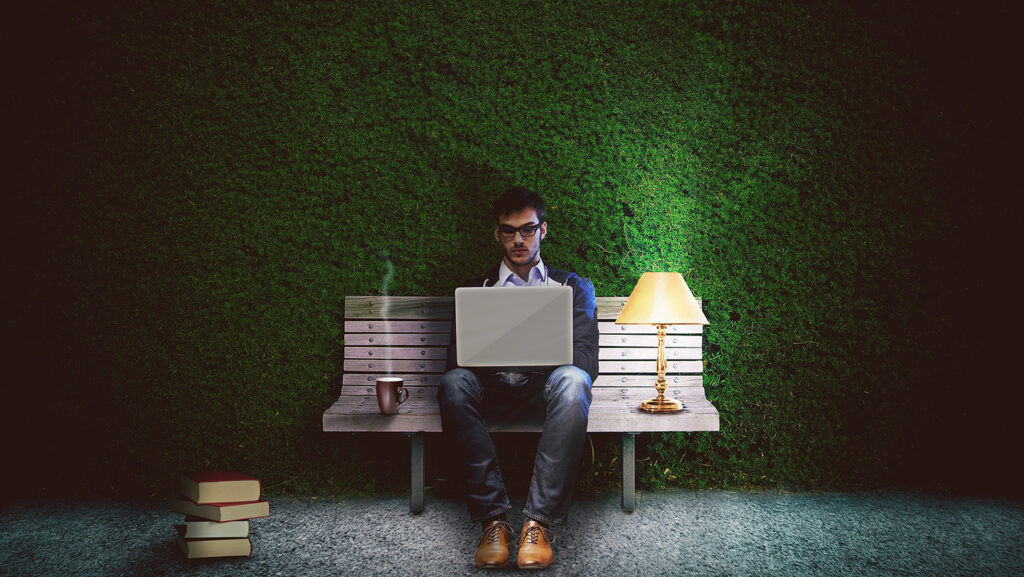人手不足で職場崩壊するとどうなる?|原因や解決方法を解説

「人手不足を解消したい」「人手不足が慢性化するとどうなる?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
近年、少子高齢化により人手不足が深刻化しているため、人材の確保が課題となっている企業が増えています。
そこで今回の記事では、人手不足で職場崩壊するとどうなるのかだけでなく、職場崩壊が起こる原因や対策も詳しく解説していきます。人手不足が課題となっている方は、ぜひ参考にしてください。
この記事をご覧の方にオススメの資料のご案内
優秀な社員が辞めない会社づくりの方法がわかる資料
人手不足に悩む中小企業が「在宅チーム」を活用することで
優秀な社員を確保し、利益率の高い組織をつくる方法のヒントが得られます。
職場崩壊寸前の3つの特徴
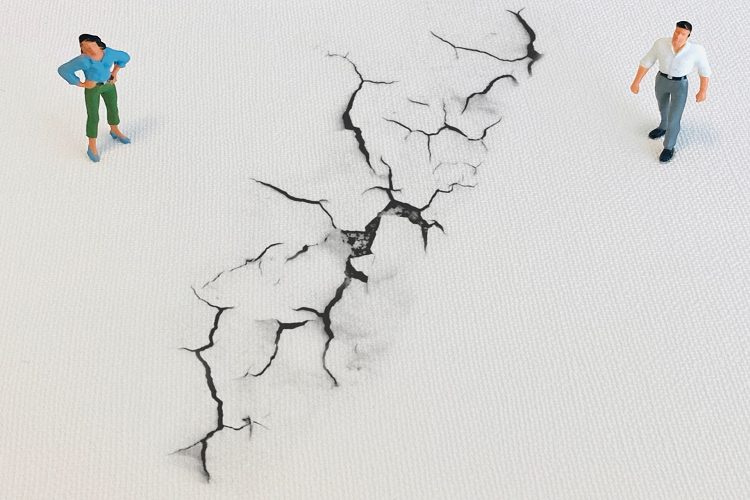
職場崩壊寸前の特徴として、具体的に以下の3つが挙げられます。
- 優秀な社員が退職する
- 社内で雑談がなくなる
- 社員への負担が増えた
下記では、それぞれの特徴を詳しく解説します。
優秀な社員が退職する
優秀な社員ほど、会社や職場の違和感に気づきやすいため、次々に退職していく可能性が高いといわれています。また、能力もあるため次の職場も見つかりやすく、今の会社にしがみつく必要がありません。
社員への負担が増えた
優秀な社員が相次いで退職してしまうと、退職者が対応していた業務を既存の社員が対応することになります。業務の負担が増えると、残った社員の精神的な負担も大きくなります。
また、業務量が増えるため、時間外労働の増加にもつながるでしょう。時間外労働が原因となり、最悪の場合、社員の連鎖退職が発生する可能性があります。
社内で雑談がなくなる
今まで普通にしていた雑談がなくなることは、職場の雰囲気が悪くなっている可能性があります。
優秀な社員が退職し、長時間の時間外労働などで、社員のモチベーションは下がってしまいます。終わらない業務も多いため、結果的に組織全体の雰囲気が悪くなります。
人手不足で職場崩壊するとどうなる?

人手不足で職場崩壊すると、下記のような事態が起こります。
- 企業自体が倒産する
- 慢性的な残業や休日出勤
- 社員や管理職が相次ぎ退職する
下記では、それぞれの事態を詳しく解説します。職場崩壊する前兆があったら、すぐ現状の課題を解消することが重要です。
企業自体が倒産する
人手不足で職場が崩壊すると起こる事態として、企業自体が倒産することが挙げられます。
人手不足が深刻化している場合、そもそも業務が回らないため、企業自体が倒産してしまう可能性が高いです。
慢性的な残業や休日出勤
人手不足で職場が崩壊することで、残業や休日出勤が慢性的に発生してしまう可能性があります。
人手不足が深刻化すると、在籍している社員が対応せざるを得ません。しかし、どんなに頑張っても法定労働時間内で処理できる業務量には限りがあります。
そのため、慢性的な残業や休日出勤を強いられ、肉体的・精神的な疲労が蓄積されると、最悪の場合、過労死になってしまうことも考えられます。過労死するまで働かせたという事実が発覚すれば、その時点で企業の存続は難しいでしょう。
社員や管理職が相次ぎ退職する
人手不足が深刻化すると、長時間労働や社内の雰囲気に嫌気がさした社員や管理職が、相次ぎ退職する可能性があります。
退職者が続出すると、さらに残された社員の負担が増えるため、負のサイクルから抜け出せなくなる可能性があります。
人手不足による職場崩壊は会社の責任

人手不足による職場崩壊は、職場崩壊を起こすまで何も対策を行わなかった企業側に責任があります。前述した通り、人手不足が深刻化すればするほど、職場崩壊を起こす可能性は高いです。そのため、企業側は早い段階で対策に取り組む必要があります。
以降の章で、人手不足で職場崩壊しないための対処法を解説しますので、自社で何ができるか考えながら、読み進めてみてください。
人手不足で職場崩壊しないための対策法

人手不足で職場崩壊しないための対策法として、具体的に以下の5つが挙げられます。
- 採用人数を増やす
- アウトソーシングを活用する
- 働きやすい環境づくり
- 納得度の高い評価制度を導入する
- 社内のコミュニケーションを活性化させる
下記では、それぞれの対策法を詳しく解説します。
採用人数を増やす
採用人数を増やすことで、仕事を分担できる体制をまずは整えることが可能です。
しかし、募集すれば簡単に人材を採用できるわけではありません。採用数が少ない場合は、採用フローの見直しが必要です。優秀な人材を確保しようとするあまり、採用の道のりが困難で、応募者が途中で離脱してしまっている場合も考えられます。また、採用難易度が高すぎるケースも非常に多いです。採用フローや採用条件を見直し、応募者数を増やす取り組みが必要となります。
採用してもすぐ離職してしまう場合は、待遇が悪い可能性があります。待遇面が原因の離職を防ぐためには、社員に不満がないかどうか調査を行います。改善の余地があれば、速やかに対応することが大切です。
アウトソーシングを活用する
業務を社内の人員だけで回せない場合は、アウトソーシングの活用も一つの手段です。アウトソーシングとは、一部の業務を外部企業に委託したり、人材派遣などの外部リソースを活用したりすることが挙げられます。
ノンコア業務をアウトソーシングすれば、従業員は本来のコア業務に専念できるようになるため、組織全体の生産性が向上します。
また、社内にノウハウがない場合でも、業務を遂行できるのがアウトソーシングの魅力です。
働きやすい環境づくり
そもそも人手不足を深刻化させないために、社員が働きやすいと感じる環境を作ることが重要です。
働きやすい環境を作るためには、以下のような方法があります。
制度の導入
テレワークや時短、フレックスタイム制を導入することで、社員はライフスタイルに合わせて働けるようになります。例えば、テレワークやフレックスタイム制であれば、出退勤のストレスを軽減することが可能です。また、時短勤務が可能になれば、子育てや介護と両立できるようになります。
福利厚生の見直し
福利厚生は社員のモチベーションを左右するものです。遠方から通勤する社員には通勤手当、家族を養っている社員には家族手当や住宅手当などがあります。子育て中の社員が利用できる託児施設も福利厚生の一つです。また、社員同士のコミュニケーションを活性化するために、食堂やカフェテリアを設置することもあります。福利厚生の内容は、企業によってさまざまです。
社内風土の改善
働きやすい環境かどうかは、社内の人間関係や社内風土で決まると言っても過言ではありません。特に、人間関係は転職理由で常に上位にランクインしています。新人社員でも発言できるような風通しの良い職場であるか、残業が当たり前になっていないかなど、まずは改善点を洗い出すことが大切です。
納得度の高い評価制度を導入する
納得度の高い評価制度を導入することで、社員のモチベーションアップにつながります。納得度の高い評価制度とは、以下のような方法が挙げられます。
目標管理(MBO)
目標管理とは、目標を設定してその達成度によって評価する方法です。定量的な目標を設定することで、定量的な結果で評価できるため、不平等なことが起こりません。また、目標を設定すると、社員一人ひとりが達成するために頑張れるようになるので、モチベーションの維持もしやすいです。
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは、実際の行動がどのような結果を生み出せたのかを客観的に評価する方法です。評価基準の曖昧さがなくなるため、評価に対して不満を抱きにくいです。
社内のコミュニケーションを活性化させる
社内の人間関係が構築されることで、社員の心理的な安心感が高まります。分からないことがあっても相談しやすいため、業務を円滑に回すことが可能です。
社内の人間関係を構築する方法として、以下の3つが挙げられます。
1on1
1on1とは、上司と部下が1対1で行う面談のことです。上司は1on1を通して、部下の悩みや将来的なビジョンなどを聞きます。定期的に行い、部下の自発的な発言を尊重することで、良い関係を築くことが可能です。
メンター制度
メンター制度とは、先輩が後輩との関係を築いたり、悩みなどを支援したりする制度のことです。上司以外にあたる人がメンターとなるため、より話しやすいのが特徴です。
慢性的な人手不足になる前に解消しよう!

今回は、人手不足による職場崩壊が起こるとどうなるのかについて詳しく解説しました。
近年、少子高齢化の影響により、人手不足に陥っている企業は多いです。人材採用も売り手市場が続いているため、募集したとしても簡単に人材を確保できないのが現状と言えます。しかし、人手不足が深刻化すると、残った社員の負担が大きくなったり、企業自体が倒産してしまったりする可能性があります。
本記事で解説した職場崩壊の特徴を感じた場合は、すぐに対策を行うことが大切です。人手不足を解消する方法は多くありますが、自社の業務フローの見直し、社員の既存業務におけるノンコア、コアの選別などは 客観的に見てもらえる第三者にアドバイスをしてもらうことで、整理がしやすいくなります。